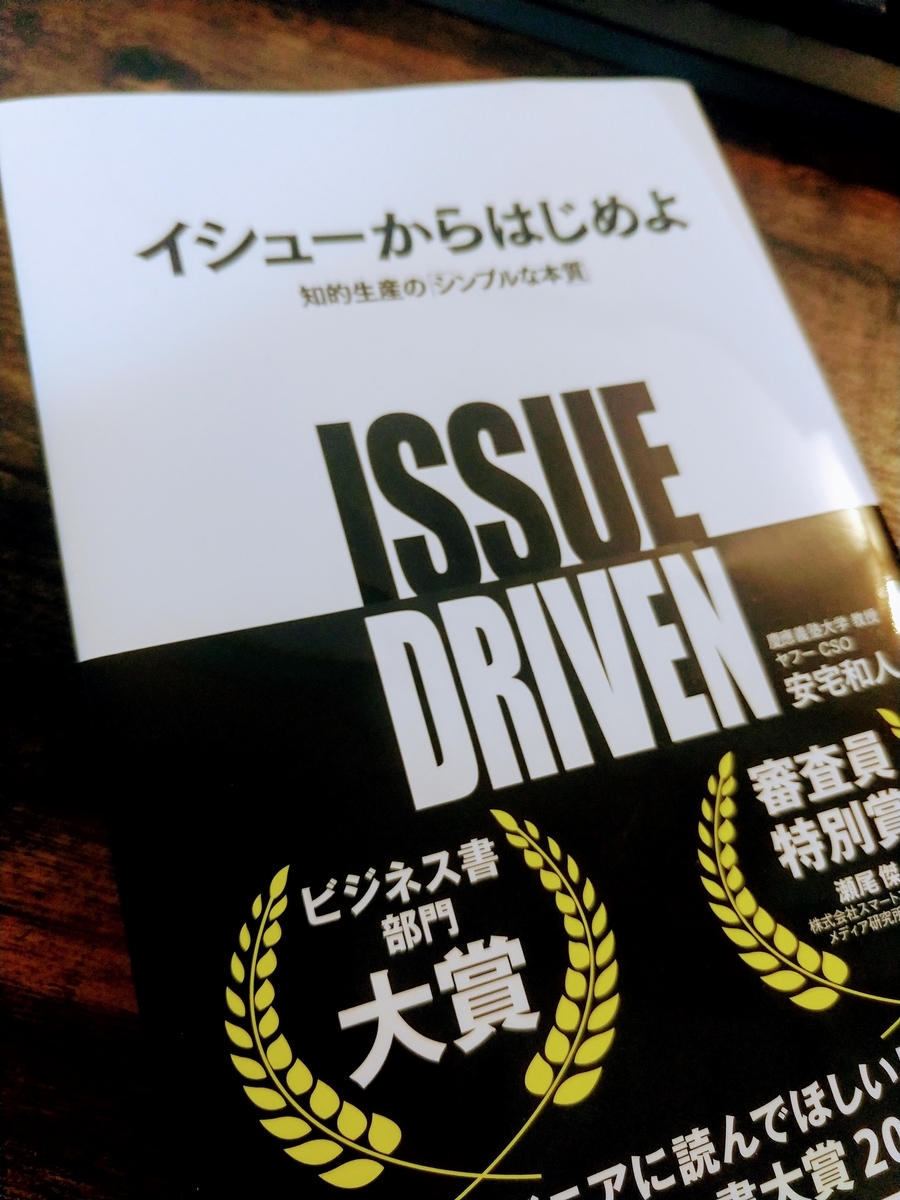

- 作者:安宅和人
- 発売日: 2014/09/01
- メディア: Kindle版
何故読んだのか
増税前に買った技術書が届いた!
— youzine (@youzine_geecul) October 6, 2019
積読もまだあるから、今月末以降から読みはじめたい pic.twitter.com/HLP2gNMql6
去年の10月には購入済みだったのを、なんだかんだ読めていなかったので読むことにした。
仕事の進め方とかに悩んでいた時期で、どうしたらいいか色々考えている中で一助になるかもと思い購入した一冊。
要約
序章 この本の考え方 -- 脱「犬の道」
本書でイシューと呼んでいるものは次の2つの定義「2つ以上の集団で決着のついていない問題」「根本に関わるもしくは白黒がはっきりしていない問題」からなる。
プロフェッショナルにとってバリューのある仕事とはイシュー度が高く、解の質が高いものである。
著者はイシュー度を「自分のおかれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ」、
解の質を「そのイシューに対してどこまで明確に答えを出せているかの度合い」と考えている。
多くの人はバリューのある仕事をするために、多くの仕事をして解の質を高めるアプローチをとるが、著者はこれを「犬の道」と呼び、推奨しない。
バリューのある仕事をするためにはイシュー度の高い仕事をしなければならない。
第1章 イシュードリブン ーー 「解く」前に「見極める」
イシュー度の高い仕事をするためにはイシューを見極める必要がある。
そのためには仮説を立てることでイシューに対して具体的に答えが出し得るようにすることで、何をしなければならないかが明確になる。
よいイシューとは自分やチームを奮い立たせることができるもので、「本質的な選択肢である」「深い仮説がある」「答えを出せる」の3つ事項を満たす。
第2章 仮説ドリブン① ーー イシューを分解し、ストーリーラインを組み立てる
第3章 仮説ドリブン② -- ストーリーを絵コンテにする
バリューのある仕事にするためにはイシューを見極め、「解の質」を高める必要がある。
そのための作業がストーリーラインと絵コンテ作りで、この2つをあわせて「イシュー分析」という。
イシューの構造を明らかにしてサブイシューを洗いだし、分析のイメージ作りを行う作業のことだ。
イシューと仮説が正しいとすると、どんな論理と分析によって検証できるか、と最終的な姿から考える。
第4章 アウトプットドリブン ーー 実際の分析を進める
ストーリーラインと絵コンテができたら、実際の分析を行う。
ストーリーラインや結論に大きな影響力を持つ部分から検証を行う。
答えありきではなくフェアに検証する。
このサイクルを早く、多く行うことで、やり直しもききやすく最終的なアウトプットの質も良くなる。
第5章 メッセージドリブン -- 「伝えるもの」をまとめる
2、3章ので下準備したストーリーラインと絵コンテを、4章で実際に情報収集、分析を行う。
5章では4章で実際に作成したアウトプットを、効果的に人に伝えられるように整理する。
アウトプットの受け手をデルブリュックの教えを引用して想定する。
ひとつ、聞き手は完全に無知だと思え ひとつ、聞き手は高度の知性を持つと想定せよ
そのうえで聞き手に「意味のある課題を扱ていることを理解してもらう」「最終的なメッセージを理解してもらう」「メッセージに納得して行動に移してもらう」必要がある。
そのために「本質的」「シンプル」という2つの視点で整理する。
感想
本書は次のような流れになっている。
序章から1章にかけてイシューとは何か、イシューとはどのように特定できるのか、
2章から3章にかけてはイシューに対してどのような答えが欲しいのかを検討し、
答えを得るためにはどのような論理構成、検討、分析やデータが必要かということを確認する。
4章で2から3章で想定した内容を実際に分析する。この段階で2章から3章で作成した内容とズレが生じた場合は、
それを取り込んで2から4章を再構成、または一部修正することをサイクル化する。
5章までに作成した内容を5章では人に伝えることを目的としてより整理する。
上記のように序章から5章まで本書の魅力は序章から1章にかけてだと思う。
多くの自己啓発書、自己啓発系SNSアカウントは膨大な量の仕事をこなすことを推奨するが、
本書では効率的に価値を高めるためにはまず本当に取り組むべきイシューを見極め、取り組むことが大事だと語る。
スライム(瑣末な問題)ばかり倒しても強くなるのは難しいということだ。難しいダンジョンに挑戦し、強敵に挑むことで強くなることができる。
しかし現実世界での問題、イシューというのはドラクエの敵キャラのように見た目に分かりやすい形やステータス表示があるわけではない。
本書ではそもそも対応すべきイシューとはどういうものか、どのようにイシューを見極めるかということを序章と1章で説明する。
本書で最も価値があるのはこの序章と1章だと思う。
多くの論理思考の本などでは問題の解き方(フレームワークやツール)は語るが、そもそも解くべき問題とは何か、どう見極めるべきかまでは語らないからだ。
イシューを見極めるためにまずはイシューに対する仮説を立てて考えることで、何が必要かを見極めることができるというのは、僕にとって新たな知見だった。
2章から4章を理解し実践するためには事前に基本的なフレームワークや論理的思考方法についての知識が必要だと思う。
どのような論理構成にすればよいかという詳細については以下の本が参考になると思う。
「仕事は選べ」「仕事は断れ」「質より量」仕事術や自己啓発で並ぶこのような言葉について再考することができます。
一度読んで終わりではなく、都度読み返しながら実践してみようと思う一冊でした。
学び
「イシュー度」の低い問題にどれだけたくさん取り組んで必死に解を出したところで、最終的なバリューは上がらず、疲弊していくだけだ
仮説を立てることで、答えを出し得るイシューとなる
言語化する=「概念をきっちりと定義するのは言葉にしかできない
なんちゃってイシューを最初の段階ではじくことが大切だ
リンク

- 作者:安宅和人
- 発売日: 2014/09/01
- メディア: Kindle版
